生物多様性

生物多様性に関する考え方
ニップングループが製造する商品の多くは、大自然の恵みに深く恩恵を受けています。このことを認識しつつ、基本方針を制定し、社員研修も含め生物多様性の保全を推進しています。
ニップングループ生物多様性方針
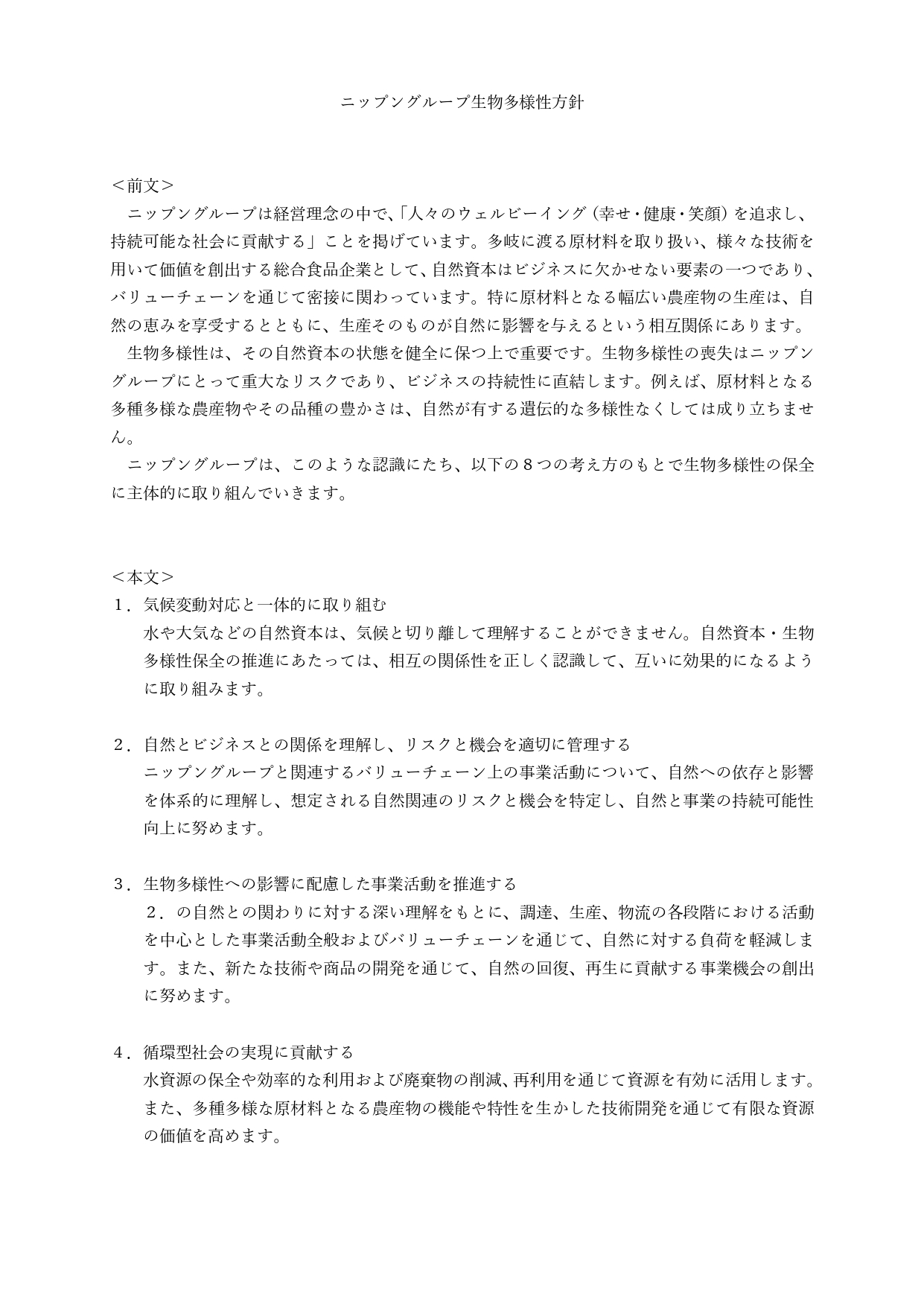
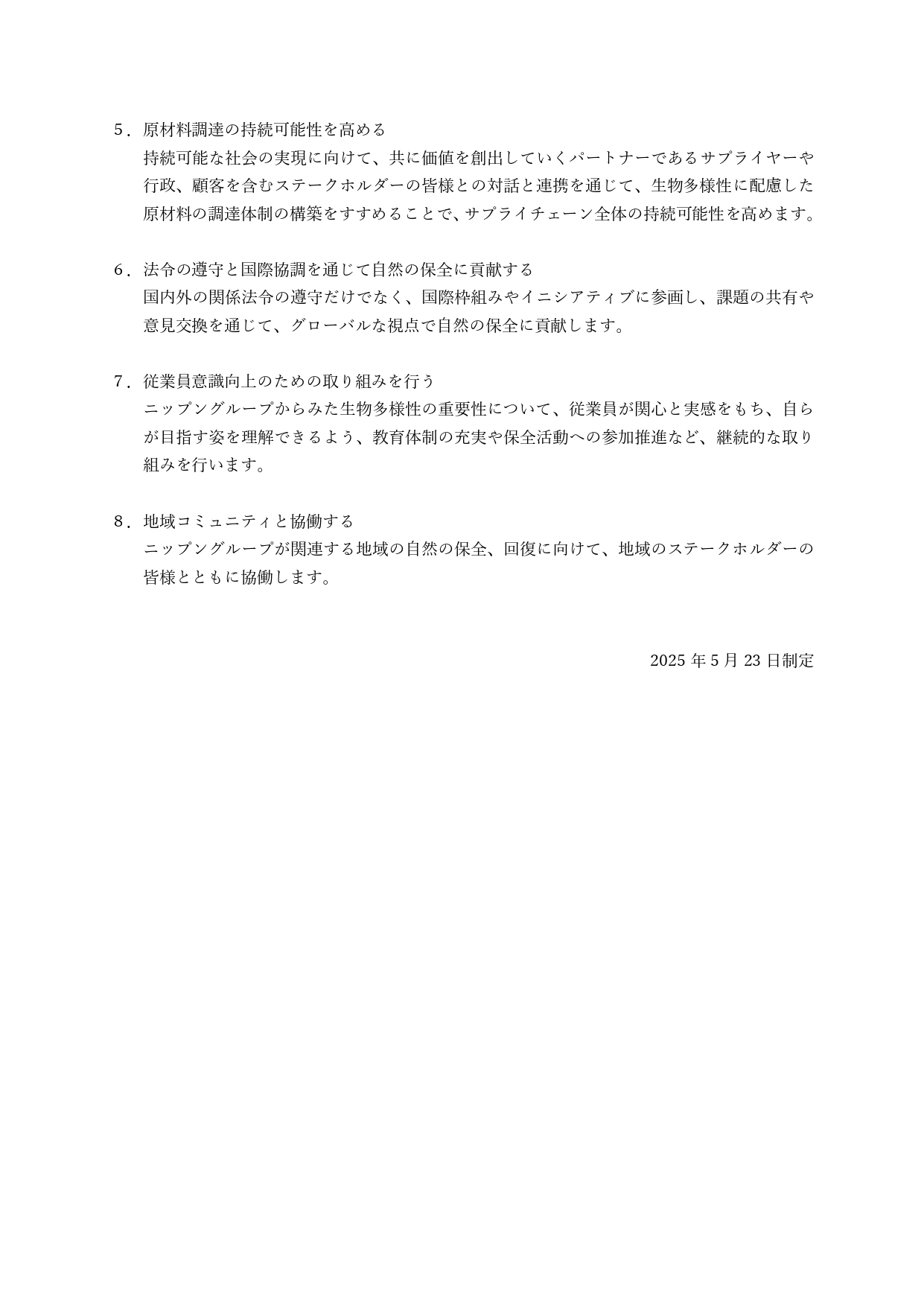
経団連生物多様性宣言イニシアチブ
当社は、「経団連生物多様性宣言」に賛同し、同イニシアチブにも参加しています。
「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」は、「経団連生物多様性宣言・行動指針(改定版)」が掲げる7項目のうち複数の項目に取り組む、または全体の趣旨に賛同する企業・団体で構成されています。
当社は、これまでも北海道にあるグループ所有の遊休地を「ニップン四季の森」として整備・解放するなど、生物多様性 保全に対する取り組みを進めてきました。また、経団連自然保護基金への資金支援も行っています。今後も、ニップンの「生物多様性に関する基本方針」に沿って、取り組みを強化してまいります。

TNFDに沿った情報開示
基本的な考え方
様々な原材料を調達し、食品を製造する当社グループにとって、自然の恵みは不可欠な存在であり、それを維持していくことは当社グループの社会的責務であると考えています。
こうした認識に立ち、当社グループは自然資本に関する検討を深めてきました。2023年に見直したマテリアティ(重要課題)には、「環境保護への取り組み」を位置づけ、気候変動への対応や生物多様性の保全、循環型社会の実現等に向けた取り組みを推進してきました。また、2024年に策定した「長期ビジョン2030」では、経済的価値と社会的価値の両立を掲げ、食の持続可能性に対する負のインパクトの軽減や、農業分野を含むサステナブルな食料システムの構築等を標ぼうしています。2025年5月23日に「ニップングループ生物多様性基本方針」を制定し、自然資本に関する認識や行動を明確化しました。
さらに、こうした方針等の実現に向け、当社グループ事業と自然との関わりや、そこにおけるリスクと機会の検討を行ってきました。この取り組みは、当社グループの強みである「原材料の調達力」や「食品の加工技術力」を一層高めるとともに、持続可能な社会の実現への貢献に向けて不可欠であると考えています。
また、当社グループは自然関連財務情報開示タスクフォース(以下TNFD※1)の理念に賛同し、2025年8月にTNFDアダプターに登録しました。以下、TNFDの開示提言に基づき、「ガバナンス」、「戦略」、「リスクと影響の管理」、「指標と目標」の4つの柱のうち、「ガバナンス」、「戦略」、「リスクと影響の管理」について開示します。
※1:TNFDは、企業が自然資本や生物多様性に関するリスクや機会を評価・開示するための枠組みを開発・提供する国際イニシアチブ
TNFDへの対応 サマリー
| 項目 | 内容 |
| ガバナンス | (1)体制当社グループは、サステナビリティに関する課題を重要な経営課題として位置付け、その検討および対応のための体制 を構築しています。 ●「サステナビリティ委員会」は、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含めて構成。サステナビリティに関するリスクや機会の監視・統制を担い、当社グループの方向性、マテリアリティおよび戦略のあり方を審議して取締役会へ答申します(年2回程度開催)。 ●取締役会は、答申を踏まえ、マテリアリティの承認およびサステナビリティを踏まえた基本戦略を決定します ●「サステナビリティ実行委員会」は、サステナビリティ関連のリスクや機会の識別・評価・管理を担います。下部組織として、環境課題を横断的に検討する「環境部会」を設置。2024年度には環境部会内に「生物多様性タスクフォース」を組織し、グループの事業と自然との関わり、およびリスクと機会について検討しました。 (2)ステークホルダーとの関わり ●自然との相互作用にも配慮した持続可能なサプライチェーンの構築には、多様なステークホルダーとの適切な協働が不可欠であると認識しています。 ●「ニップングループ調達基本方針」を制定し、その中で人権・労働安全衛生への配慮、環境負荷の低減、生物多様性への配慮等を掲げています。 ●サプライヤーの皆様との適切な協働を推進するため、「サプライヤーの皆様へのお願い」を制定し、強制労働・児童労働の排除、温室効果ガスの削減、生物多様性への配慮など、人権および環境に関する要請事項を設定しています。 |
| 戦略 | TNFDが推奨するLEAPアプローチに基づいて検討。 ■Scoping:対象とする経済活動の設定 ●製粉事業および食品事業における直接操業と、バリューチェーンの上流から下流までを対象として、事業活動と自然資本との関連性を分析。 ●原材料のうち、調達金額が大きく、かつ自然への依存や影響も大きいと想定される5つの作物(小麦、サトウキビ、米、トウモロコシ、パーム)を選定。 ■Locate:自然との接点の発見 ●各対象作物の主要調達国における自然の状況と、対象活動による自然への依存・影響をENCOREで評価。 ●サトウキビの主要調達国であるタイでは、農業における水リスクおよび生物多様性リスクがともに高い。 ●アメリカ(小麦・トウモロコシ)やオーストラリア(小麦・サトウキビ)では、農業の水リスクが高い。 ・マレーシア(パーム)では、生物多様性リスクの高さが目立つ。 ■Evaluate:依存と影響の評価 ●原材料生産においては、各対象作物とも、土壌、動植物、大気・気候、水といった多様なカテゴリーで「非常に高い(VH)」または「高い(H)」項目が多く、原材料生産は自然のあらゆる要素に大きく依存し、また大きな負荷を与え得ることを再認識。 ●食品加工においては、清浄で一定量の水の安定供給を支える自然の要素が重要であり、水への依存が多岐にわたることが示唆された。 ■Assess:リスクと機会の評価 ●リスクとなり得る自然/社会の変化として、以下の8項目を抽出。 <依存> 1. 温暖化による栽培適地の変化(慢性) 2. 農業用水の劣化/枯渇(慢性) 3. 農業における天候被害の頻発(急性) 4. 工場の取水流域の劣化(慢性/急性) <影響> 5. 堆肥・農薬などの農業資材の利用に関する規制強化(政策/批判) 6. 農地開拓・利用に関する規制強化(政策/批判) ENCOREからは導出されないが重要と想定される社会変化 7. プラスチック利用削減への社会的要請の高まり(政策/批判) 8. 食品ロス削減への社会的要請の高まり(政策/批判) <リスクの具体化と対応策> ●上記8つの変化について、具体的に生じ得るリスクと対応策を検討。 ●原材料生産においては、主要調達国の水リスク評価などを通じて物理的リスクを定期的にモニタリングするとともに、農業の環境負荷低減への貢献や持続可能な調達の取り組みを引き続き推進。 ●製粉・食品加工においては、水に関する物理的リスクに対し、節水による水利用の効率化を図る。 ●水資源保全に関する社員の意識啓発も見据え、群馬県での植樹活動による水源涵養に取り組む。 ●プラスチック利用削減や食品ロス削減に対する社会的要請には、「eco紙トレー」の導入や、工場で生じる副産物のアップサイクル活用等で対応の充実を図る。 ※今後、分析対象の拡大と深化を図る。 |
| リスクと インパクトの管理 | ●重要性の高い代表的なリスクとして設定した18の主要リスクに対し、軽減策の検討等を実施。 ●これら18の主要リスクには「気候変動」や「原材料の調達」といった自然資本と関連の深いリスクが含まれ、いずれも「顕在化した場合の経営資本への影響が大きい特に重要なリスク」として位置付けている。 ●サステナビリティ関連の課題は、前述のガバナンス体制のもと、サステナビリティ委員会およびサステナビリティ実行委員会を中心に検討・対応を行う。 |
| 指標と目標 | 今後策定。 |
ニップン四季の森
「ニップン四季の森」プロジェクトは、生物多様性保全や温暖化防止に向け、ニップングループが進める取り組みです。北海道深川市に当社グループのニップンソリューション㈱が所有する遊休地を四季の自然が楽しめる森に少しずつ整備して解放し、生態系保全のモデルケースにするために2011年から取り組みを開始しました。
毎年の植樹祭では、地元市民の皆さんにもご参加いただいており、エゾヤマザクラやナナカマド等を植樹しています。

植樹祭
原材料栽培
当社グループの㈱ナガノトマトでは、長野県産のえのき茸のなめ茸製品やトマトケチャップなどのトマト加工製品を製造・販売しています。商品の中でも、トマトジュース「信州生まれのおいしいトマト」は、地産地消の推進を図るため、100%長野県産のトマトを使用しています。
また、サステナビリティ経営推進の一環として、毎夏、当社社員はトマトの収穫を実施することで、社会的貢献に対する意識向上を図っています。今後もサステナビリティ経営を意識した活動に取り組んでいきます。

トマトの収穫

信州生まれのおいしいトマト
